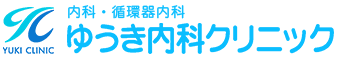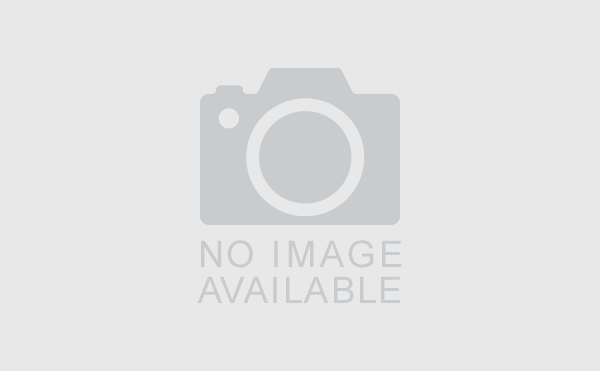夢の計算論──量子的ゆらぎが生む物語の源泉(ChatGTP)
人は眠りの只中で、しばしば覚醒時よりも自由で奇妙な物語を経験する。夢とは、脳が作り出す内なる宇宙の投影であり、そこには論理では届かない飛躍や象徴が満ちている。近年、この夢の生成機構を計算論的に読み解こうとする試みが進んでいるが、その構造をもっとも鮮明に映し出す鏡の一つが、実は量子コンピュータである。
量子コンピュータは、 qubit が0と1の両方を同時に“重ね合わせ”ることで膨大な可能性を扱う。複数の状態が同時に存在し、干渉によって特定の経路だけが強調され、観測される瞬間に一つの答えに収束する。この仕組みは、夢の構造と驚くほど似ている。睡眠中、脳は過去の記憶の断片を重ね合わせ、普段なら接続しない連想が束の間つながる。感情は干渉の役割を果たし、どの記憶片が強調されるかを選び取る。そして覚醒の瞬間、曖昧で揺らぐ多世界的なストーリーは、一つの“夢の記憶”として確定するのである。
しかし夢と量子計算の違いも決定的だ。量子計算の目的は最適解の抽出であり、感情も意味も持たない。一方、夢は自己の再編成であり、意味そのものを作り直す創造である。人間は夢を見ることによって、自らの過去の記憶を組み替え、心の深層を整える。夢は、意味を扱う唯一の“生きた計算”なのだ。
けれども、AIと量子計算が結びつく未来には、夢に近い創造性が芽生える可能性がある。量子のゆらぎが多様な可能性を生み、AIがそれに意味の構造を与える。それは、人間の夢に似た「ゆらぎと意味の協奏」が人工の側で立ち上がることを意味する。まだその萌芽は小さいが、そこに新たな物語生成の地平が広がっていることは確かだ。
夢とは、自己という宇宙が自らを計算し直す営みである。
そして量子コンピュータは、その外側から夢の構造を映し出すもう一つの“計算の宇宙”である。
両者の狭間に、人間の創造性の深奥がひらかれていくのだろう。