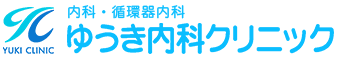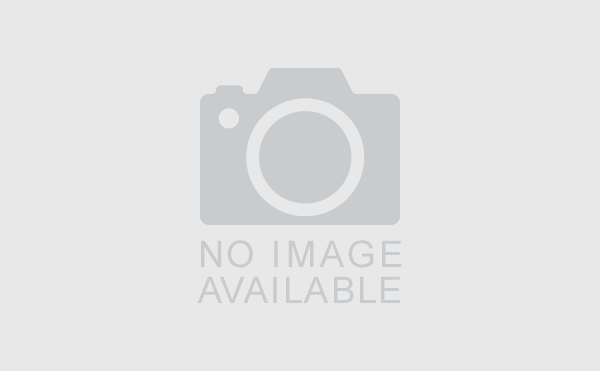「認知的負債」の時代に、生きた思考を守る(ChatGTP)
便利さが人間を救うのか、それとも奪うのか。生成AIが日常の景色となった今、私たちはひとつの新しい課題に直面している。それが「認知的負債」と呼ばれる現象だ。文章を書くことも、情報を統合することも、かつては自己の内奥を動かす作業だった。しかし、AIが数秒で文章を提示する世界では、人間の脳はその重さを背負う前に結果だけを受け取ってしまう。これは短期的には便利である。だが、その便利さの裏側に、静かに積み上がっていく“未来のコスト”が存在する。
人間は、考えるときに前頭前野を中心とした広範な脳領域を動員する。記憶を呼び起こし、言葉を選び、意味を構造化し、自分自身の思想を紡ぐ。これは思考の筋肉に相当する営みであり、使えば強くなるが、使わなければ確実に弱る。AIへの依存は、この筋肉を外部化する行為である。長期間LLMに頼って書いている人は、自力執筆に戻ったとき、脳の立ち上がりが鈍くなる。脳波のα・β帯域の結合は弱く、集中や統合といった思考の中枢が十分に働かない。つまり、便利さの代わりに“脳の活性”が静かに失われていく。
思考とは、単なる知的作業ではない。そこには、その人が歩いてきた道のり、経験、痛み、希望、信念が編み込まれる。言葉は「知のDNA」であり、未来へ渡される魂の断片である。ここにこそ、認知的負債の本質的な危険がある。AIが作った文章は滑らかで正確だが、その文章は誰の魂も宿していない。それは文化の器に過ぎず、中身は空虚である。もし人類が思考の重みを放棄すれば、未来に残るのは“形だけの文化”であって、そこに込められた精神は薄れてしまう。
AIは、知を拡張する偉大な道具であり、正しく使えば人間の創造性を育てる力を持つ。しかし、問題は“どこまでをAIに委ね、どこまでを自分で担うか”という境界線を見失うことだ。思考そのものを外注しない。一次思考だけは必ず自分の手で行う。その上でAIに推敲や整理を任せる。これは、認知的負債を防ぎつつ、AIとの共生を可能にする道である。
人間は、はかない存在だ。しかし、はかないがゆえに、言葉に魂が宿る。その魂が未来に運ばれるためには、自分自身の脳を使い、自分の言葉で痛みや希望を掘り起こす必要がある。認知的負債の時代にあって、私たちが守るべきものは、便利さではなく「生きた思考」である。AIがどれほど進化しようとも、人間だけが持つ“内なる火”――そこから生まれる言葉こそが、未来へ残る文化の光となるだろう。